そして、その陰に吉野の山林王がいたということを。
.jpg)
.jpg)
新発掘の若い頃の写真(左)と、写真館で洋装した写真(右) なかなかイケメン
「明治」をつくったのは、林業だということを知っていますか?
そして、その陰に吉野の山林王がいたということを。
.jpg)
.jpg)
新発掘の若い頃の写真(左)と、写真館で洋装した写真(右) なかなかイケメン
土倉庄三郎は、三井家に匹敵すると言われた財力を、国のために注ぎました。自由民権運動に、大学設立など教育に。そして国土の緑化に。その生きざまと、終焉を描きます。
森と近代日本を動かした男
山林王・土倉庄三郎の生涯
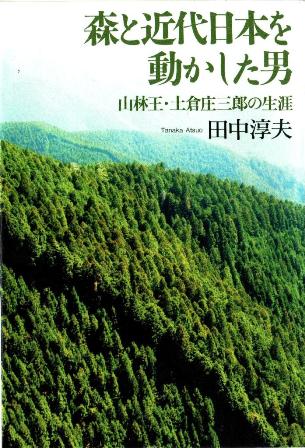
**********************************************************
著者 田中 淳夫
出版元 洋泉社 03-5259-0251
定価 本体2500円+税
発売日 2012年11月 7日
ISBN978-4-8003−0043−0
帯文
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
苦節7年。ようやく完成させた土倉庄三郎の評伝である。
思えば、森林ジャーナリストの道を歩むきっかけとなった奈良県川上村の訪問時に、最初に迎えてくれたのが、「土倉翁造林頌徳記念」の巨大な磨崖碑であった。それ以後、どんな人物か気にはなっていたが、伝えられている情報で表面だけをなぞるように理解していた。そして森林や林業そのものを描くことに邁進していた。
思えば、その時期があったからこそ、土倉庄三郎を描く決心がついたと言えるだろう。もし、そうした基礎知識なしに彼の生涯に取り組んでも、肝心な部分で理解できない、あるいはトンチンカンな解釈をしてしまったかもしれない。ただ、いくら調べても隔靴掻痒、根っこの部分がつかめなかった点は多々ある。また調べれば調べるほど深みにはまる感もあった。
背景となる明治の社会情勢だけならまだしも、翁と関わった人々や、子息・孫子らの人生まで踏み込み出すと、もはや収拾がつかなくなる。ある意味、涙を飲んで、まずは庄三郎自身の歩みを記録すべく絞り込み、まとめることができた。おかげで、執筆した原稿を半分以下に削るきつい作業も行ったが、まずは世間に問うことを最優先にしたのである。
内容に関しては、
本HPの土倉庄三郎ページ
拙プログの土倉庄三郎カテゴリー もしくは取材・執筆・講演カテゴリーの2012年10月を中心とした記事
さらに拙裏ブログの各所(幻の写真カテゴリーなど)にも記しています。
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
【目次】
はじめに
【序 章】吉野川源流の村へ、五社峠を歩く
【第一章】自由民権運動を駆け抜ける
1 板垣退助の謎の洋行費
2 自由民権運動の台所は大和にあり
3 朝鮮からの亡命者・金玉均と樽井藤吉
4 衆議院議員選挙と『大東合邦論』
5 婦人運動家・景山英子と本因坊秀栄
6 同志社と日本女子大学の設立支援
【第二章】まつろわぬ山の民の歴史
1 吉野の山々と敗者の系譜
2 土倉家の出自と姓名
3 頭角あらわした庄三郎
4 林業修業と?口銀?廃止運動
5 薪にされかかった吉野山の桜
【第三章】大和の国を改造する
1 林業の要は?運搬?にあり
2 「青山二〇分の一」の策
3 大杉谷と大台个原、そして土倉街道
4 大和の養蚕は川上村にあり
5 奈良公園に吉野の美林を
6 吉野の筏を内国勧業博覧会へ
7 吉野林業と土倉家の経営手腕
【第四章】「日本の林学の父」と明治の林政
1 東京帝大教授・本多静六の苦学力行
2 明治期日本の森林事情
3 日清戦争と「年々戦勝論」
4 『吉野林業全書』の刊行
5 『林政意見』を世に問う
6 吉野の森を全国へ
7 大日本山林会の吉野視察
【第五章】土倉家の六男五女と還暦事業
1 洋服を着た小学生たち
2 同志社と芳水館の教育
3 女子教育への情熱と娘の留学
4 五人の娘たちの結婚
5 大陸を夢見た長男・鶴松
6 次男・龍次郎、台湾の山林王に
7 「樹喜王」の還暦祝い
【第六章】逼塞と晩年の輝き
1 六郎の若死と忍び寄る影
2 屋台骨を揺るがした鶴松の事業
3 龍次郎の台湾引き揚げ
4 孫たちから見た庄三郎
5 庄三郎、最後の造林
6 後南朝にかけた村民の誇り
7 庄三郎の死
【第七章】庄三郎なき吉野の行方
1 鎧掛岩に「頌徳記念碑」の建設
2 大山主になった本多静六の足跡
3 カーネーションの父・龍次郎
4 次女・政子と西太后との親交
【終 章】残り火──吉野ダラーと大滝ダム
土倉庄三郎関連年表
あとがき
参考文献
δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ
<中身紹介>
はじめに
「土倉さんの植えた木は、チェンソーのバーを入れたらすぐわかるな」。
奈良県の吉野川源流部に位置する川上村。この村の伐採名人に土倉庄三郎の話を聞くと、そんな声が返って来た。
切れ味が違うのだそうだ。刃がすっと入り、スムースに動く。年輪幅が等間隔で、節もないからだろう。しかも幹が正円で真っ直ぐ伸びているから重心も読みやすい。大径木は倒す方向を制御するのが難しいのだが、抜群に素性がよいのだという。
もともと吉野のスギやヒノキは、緻密な手入れを施すことから、その材質のよさが売り物だ。しかし、その中でも土倉庄三郎の育てた木は別格なのだとか。
土倉庄三郎が亡くなったのは一九一七年。彼が現役の頃に造林した木となると、樹齢は一〇〇年以上になるだろう。生前は林業の斯界で知られた存在だった彼も、木が育つ間に忘れられ、今や地元でさえ名前や業績を示すものは少なくなっている。しかし、育った大樹に彼の偉業が刻まれていたのである。
私は、人と森林の交わりについて興味を持ち追い続けている。街に住む現代人は、森林や林業を遠くの世界と感じがちだが、森林は人類の歩みに欠かせなかったし、人の営みは森林環境に多大な影響を及ぼしてきた。その結果として、今の世界があると信じている。
とりわけ日本の国土と歴史は、森林の存在を外して考えられない。その森林は、林業抜きには語れない。明治という時代は、今と比べ物にならないほど林業が国土にインパクトを与えてきたし、経済や政治、国民の生活にも大きく響いたのである。そして日本の林業は、吉野林業抜きでは論じられない。庄三郎は、吉野林業を大きく発展させ全国に広めた立役者だ。だから彼の足跡を追うことで、近代国家に脱皮しようともがいていた日本に、森林や林業が果たした役割を描けるかもしれないと思いついた。
同時に山村が輝いていた時代を示したい。現在の山村は、経済的に苦境に陥り、人口減や高齢化に苛まされ極度に疲弊している。だが山村が日本の社会をリードしていた時期があるのだ。そのことを知って、再び山村に誇りを取り戻せないか。
そのためにも、まずは土倉庄三郎の実像を知っていただきたい。
δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ
本書は絶版になりました。そこで改訂版複製本として『樹喜王 土倉庄三郎』を出版しました。この本については、こちらのページを見てください。
※『樹喜王 土倉庄三郎』も、残部が少なくなったことで、新たに書き下ろし『山林王』(新泉社)を出版しました。
ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
トップ 田中淳夫の著作世界
『不思議の国のメラネシア』 /『チモール 知られざる虐殺の島』/『イノシシと人間』//『山が学校だった』
『「森を守れ」が森を殺す!』/『伐って燃やせば「森は守れる」』/『いま里山が必要な理由』 /
『日本の森はなぜ危機なのか』/『だれが日本の「森」を殺すのか』『田舎で起業!』/『田舎で暮らす!』/
『森林からのニッポン再生』/『『森を歩く 森林セラピーへのいざない』』/『ゴルフ場は自然がいっぱい』 /
『森林異変』/『日本人が知っておきたい森林の新常識』